独自治療法で救肢率を向上
 加齢に伴い誰にでも認められる動脈硬化。動脈硬化による血流障害が冠動脈に生じると狭心症や心筋梗塞、脳血管だと脳梗塞となるが、下肢血管に生じるのが閉塞性動脈硬化症だ。閉塞性動脈硬化症がさらに進行すると重症下肢虚血となり、この場合、生命予後は不良。約半数は診断されてから5年以内に亡くなるとされる。これは治療成績が向上した一部のがんよりも悪い数字で、その大きな要因は下肢切断だ。
加齢に伴い誰にでも認められる動脈硬化。動脈硬化による血流障害が冠動脈に生じると狭心症や心筋梗塞、脳血管だと脳梗塞となるが、下肢血管に生じるのが閉塞性動脈硬化症だ。閉塞性動脈硬化症がさらに進行すると重症下肢虚血となり、この場合、生命予後は不良。約半数は診断されてから5年以内に亡くなるとされる。これは治療成績が向上した一部のがんよりも悪い数字で、その大きな要因は下肢切断だ。国内では年間約3万人が何らかの事情で下肢を切断。このうち半数が重症下肢虚血による切断と推定されている。例えば糖尿病患者の場合は、下肢切断により運動療法が困難となり糖尿病が進行。高齢者では義足をつけても歩けないケースがほとんどなので、残った下肢も重症下肢虚血となる場合が多い。両足切断となると寝たきりを余儀なくされ、感染症などで死に至る。 浦澤医師も「重症下肢虚血はいかに足を残すかが、生存率およびQOL(生活の質)の向上に重要だ」と語る。
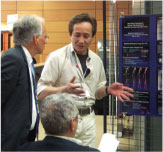
しかし厄介なのは、重症下肢虚血という病気が医師にも浸透していないことだ。患者も医師も病名を知らないまま下肢切断に至るケースも少なくない。
閉塞性動脈硬化症の初期症状は、歩くと足がだるい、常に足が冷たいなどで、進行すると足に痛みを感じるようになり、皮膚の色が黒くなったり、傷が治りづらくなる。このため患者は足の異常と思い、歩行で足がだるい場合は整形外科、傷が治りづらい場合は皮膚科を受診する。そして重症下肢虚血と診断されないまま、下肢切断となるのだ。
浦澤医師は「重症下肢虚血の治療で重要なのは、複数の診療科が連携を取り合うこと。当院の創傷センターには傷を診る医師が多数在籍していたことから、以前は困難とされた症例にもカテーテルによる治療が可能となった」と語る。
閉塞性動脈硬化症の治療は大きく分けて2つある。
1つは血管外科によるバイパス手術。人工血管や患者自身の静脈を動脈の代わりにして詰まっている部位を迂回してつなぎ、血液の流れる新しい道をつくる。
そしてもう1つは、バルーンと呼ばれる風船状の器具とステントという網目状の金属製の筒を用いて動脈を広げ、血流を回復させるカテーテル治療だ。20年もの間カテーテル治療を施してきた心臓疾患を専門とする浦澤医師はその技術を生かし、閉塞性動脈硬化症にも応用。
「経側幅血行路血管形成術」「遠位部大腿動脈直接穿刺法」という2つの独自治療法を開発した。そして足先の血管からカテーテルを入れる従来法の3つを巧みに使い分け、治癒率を劇的に向上させている。

なお、浦澤医師は2010年にフランス・マルセイユで開催された学会「MEET2010」において、この治療法の報告により、最優秀賞を受賞している。

